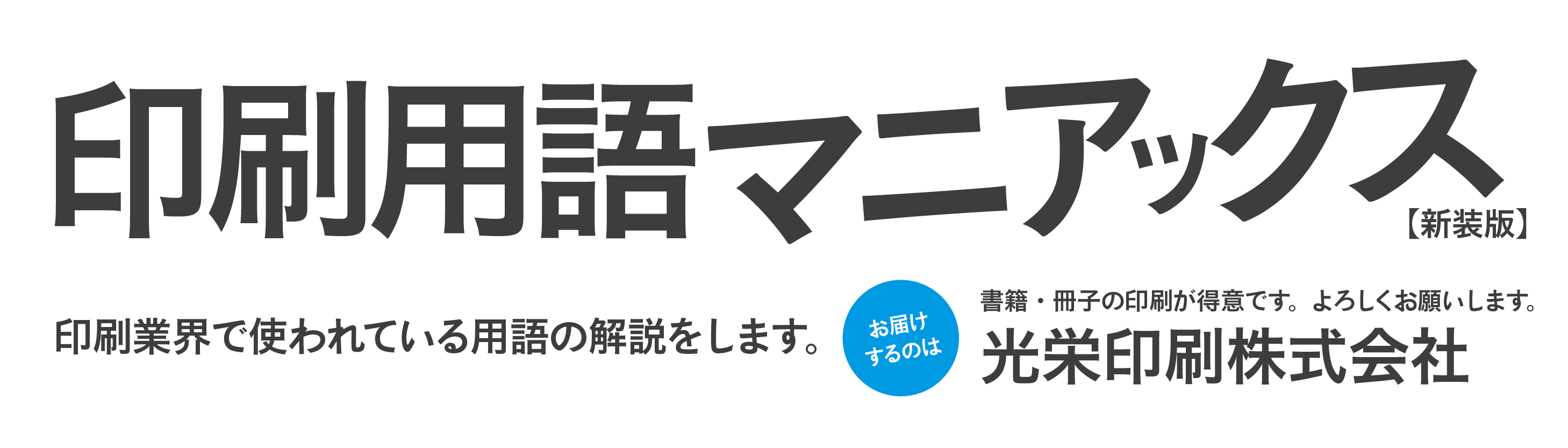「アイベルライン」は、印刷機の色見台で使われている蛍光灯の名称で、色を忠実に再現する色評価用蛍光灯。 家庭やオフィスで使われている蛍光灯は、演色評価、色温度とも色の確認には適さない。 蛍光灯の種類にもよるが、一般の蛍光灯だと赤味が弱く感じられ、人物の肌などはくすんだように見える。LEDだとなおさら。 印刷会社で色評価用蛍光灯のもとでプルーフを出力、印刷物を印刷しても、見る方の環境によっては色再現が […]
続きを読む50音順: あ行
オーバープリント(ノセ)
スミ文字、ノセ? ヌキ? オフセット印刷の製版工程では、スミ文字に「オーバープリント(ノセ)」の指定を行う。 背景に色ベタがある場合、スミ文字を「ノックアウト(ヌキ)」で製版を行うと、印刷時に少し版がずれただけで文字と色ベタの間に白い隙間が発生してしまう。印刷用紙が薄紙で、印刷時に水を吸って紙伸びを起こしてしまうような場合は、印刷現場ではどうしようもなくなる。スミ文字をノセにしておくことで、この問 […]
続きを読むあじろ綴じと無線綴じ
接着剤で本の表紙と本文を接合する製本には、「あじろ綴じ」と「無線綴じ」がある。 ■あじろ綴じ あじろ綴じでは、本文を折る際に、折丁ののど側にスリットを入れる(「あじろっぱ」などという)。 その後、接着剤で表紙と接合するが、このときに折丁のスリットに接着剤が浸透するので、本文が欠落しにくくなる。 →折丁は背がつながった状態。 スリットまでのりが浸透するので、開きに強い。ソフトカバーの書籍、コミックス […]
続きを読む大阪の色校職人エドワウ
大阪の色校職人エドワウの「色校正日記」。※注 すごく勉強になります。 会社は評価しなくても、俺は評価する。 エドワウ、応援してます。 そして「印刷虎の穴」。 みんな格好良すぎる。 成田先生の「ヤングのためのオフセット印刷雑学」、ここで知って何年か前に購入。 つるぎ出版社に電話すると、着払いで送ってもらえます。 続編出てたんですね。また注文しないと。 注:エドワウさんはブログをやめたようです。
続きを読む印刷用紙
一般の商業印刷用の印刷用紙には、次のようなものがある。 ■塗工紙 上質紙などの原紙の表面に、白色顔料を塗布したもの。塗工量が多いものから「スーパーアート」「アート」「コート」「微塗工」に分かれる。塗工面に微細な凹凸を作り、つや消し状にしたものが「ダルアート」「マットコート」。塗工量の多い方が、表面が平滑で白色度が高い。 塗工紙は、写真などの色再現性が良いので、パンフレット、ポスター、カタログ、チラ […]
続きを読む折り
■まわし折り 本文は通常、「まわし折り」で折る。刷本を裏返し(背丁の付いていない方にし)最も若いノンブルがある方を手前に持ってくる。右側を持って手前に折り、右に倒す。また右側を持って手前に折り、右に倒す。最後にもう一度右側を持って手前に折れば16頁折が完成する。 ちなみに、下の図は右びらきの場合。右びらきの折丁は地袋(下に袋がくる)。左びらきの折丁は天袋(上に袋がくる)になるように面付けする。 ■ […]
続きを読む板紙の表記【いたがみのひょうき】
一般の印刷用紙は625×880mm(A判)というようにミリメートルでサイズを表記するが、コートカードなどの板紙は80×110cm(L判)というようにセンチメートルでサイズを表記する。 また、一般の用紙は1,000枚を1連(1R)とするが、板紙では100枚を1連とし、これについては間違いやすいので、1BR(ビーレン)と表記する。
続きを読む印刷用紙の表記【いんさつようしのひょうき】
印刷用紙は次のように表記する。 ■連量 同じ銘柄の用紙でも、サイズ(菊判、四六判、A判、B判ほか)、目(T目、Y目)、連量(いろいろ)を各種取り揃えており、バリエーション数は多数になる。例えば、ニューVマット(三菱製紙)には、輪転印刷用の巻き取り用紙まで含めると全部で34種類のバリエーションが存在する。 用紙のバリエーションのうち、やや分かりづらいのが「連量」。連量は用紙の厚さを分かりやすく表すも […]
続きを読む色校正【いろこうせい】
色校正には主に3つのタイプがあり、それぞれの性質を考慮した上で、どれを採用するかを決定する。 ■本紙校正(平台校正) 校正機という校正刷り専用の機械で、本紙(本番の印刷で使用する用紙)に印刷する。 校正機は、実際の印刷機と構造が異なり、オペレーターが手でローラを動かして1色ずつ印刷している場合が多い(4色いっぺんに印刷する校正機もある)。最初に刷ったインキが乾いてから次のインキを印刷するので、イン […]
続きを読む折丁【おりちょう】
書籍、雑誌などの本文は、通常16頁単位で大きな用紙に面付けした状態で印刷する。これを機械で折ってページ順にしたものを「折丁」という。
続きを読む