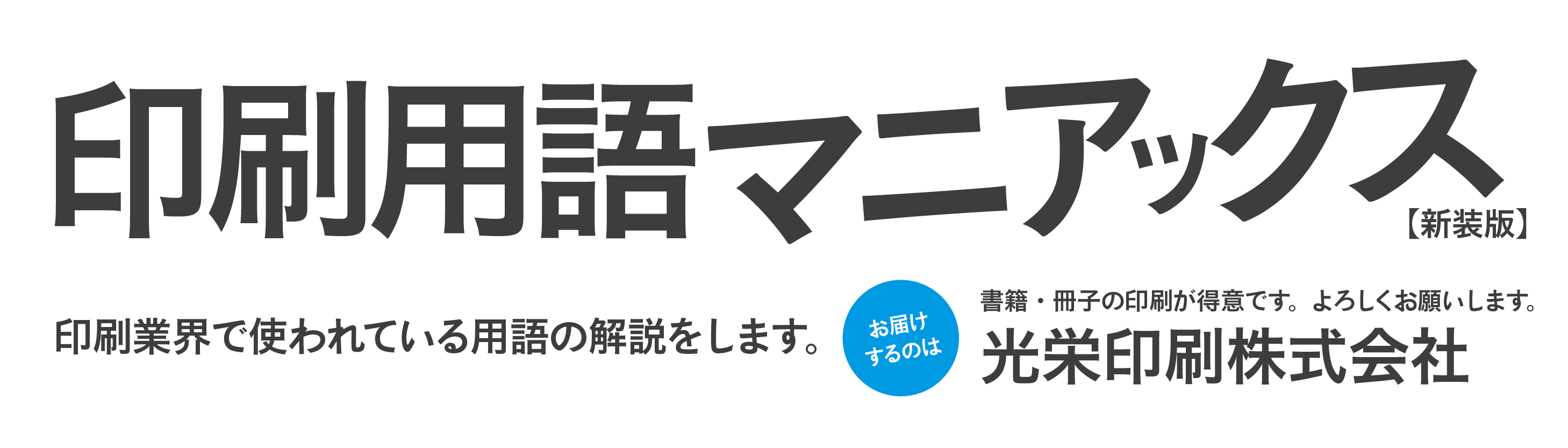「2丁がけ」とは、同じものを天地方向に2面付けして印刷する方法。 ポケット本などは、サイズが小さいので折り機や綴じ機を通らない。 このような場合、2丁がけで印刷・製本し、最後に切り離す。 また、手帳・ノートなど、本文の見開きに渡って罫線が引いてあるものも、2丁がけで印刷する。 罫線は、通常の16頁折り加工を行うと用紙の厚さが影響して、見開きにしたときにずれてしまう。 そのため、2丁がけの「平行まわ […]
続きを読むジャンル: 製本
貼り込み【はりこみ】
書籍は通常16頁単位で印刷し、折り機でページ順になるように折る(折ったものを「折丁」という)。その後、折丁を1折、2折というように順番に重ねていって(「丁合」という)、1冊分にまとまったものを表紙でくるみ、本の完成となる。 本文を16頁で割っていって、余る分は8頁、もしくは4頁、2頁で印刷を行うが、自動で丁合をとれるのは4頁までなので、2頁のペラは事前に16頁の折丁の最後のページに貼り込んでおき、 […]
続きを読むノンブル
書籍の本文で、ページの下部などにあたまから通してふるページ番号のこと。 デザイン上の制限でノンブルをふれない場合や、コミックスなど紙面いっぱいに絵柄を印刷する印刷物の場合は、版面の外に「捨てノンブル」を印刷し、面付けの間違いを防止する。 口絵や巻頭を別章扱いとする印刷物の場合は、巻頭部分にⅰ、ⅱ、ⅲなどとローマ数字のノンブルを入れる場合がある。
続きを読む折丁【おりちょう】
書籍、雑誌などの本文は、通常16頁単位で大きな用紙に面付けした状態で印刷する。これを機械で折ってページ順にしたものを「折丁」という。
続きを読む乱丁・落丁【らんちょう・らくちょう】
書籍などの印刷物で、製本の際にページの順番がばらばらに綴じられてしまうことを「乱丁」、一部のページがそっくり抜け落ちてしまうことを「落丁」という。 通常、書籍の本文は大きな用紙に16頁単位で面付けして印刷する。 次にこれをページの順番どおりになるように折る。 例えば160頁の本文は、16頁単位で折られた折丁、1~10折で構成されている。1折から10折までを順番に丁合して綴じるのだが、順番を取り違え […]
続きを読むPP貼り【ピーピーばり】
書籍のカバーや表紙には、耐久性を持たせるために印刷後にPP(ポリプロピレンフィルム)を貼ることがある。 PP貼りを行うと、加工前と見た目の色が変化する。光沢PP(クリアPP)を貼ると、加工時の熱の影響で赤っぽさが増したように見え、つや消しPP(マットPP)を貼ると、光の乱反射の影響で、色が白けて見える。 仕上がりの色味を重視する印刷物の場合は、事前にPPを貼った状態で色校正を行う。 PP貼り加工の […]
続きを読む束【つか】
書籍の背幅のことを「束(つか)」とよぶ。 ケース付きの書籍などの装丁を行う際は、実際に使用する用紙を使って事前に「束見本」というサンプルを作る。その上で、ケースの設計、試作をしたり、表紙周りのデザインを行う。試作をしないと、ケースに入れた際にスカスカだったり、キツキツだったり、支障が出ることがある。 背幅の計算は大事で、カバーや表紙は背幅を考慮して作らないと、製本時に小口側の絵柄が足りなくなったり […]
続きを読む