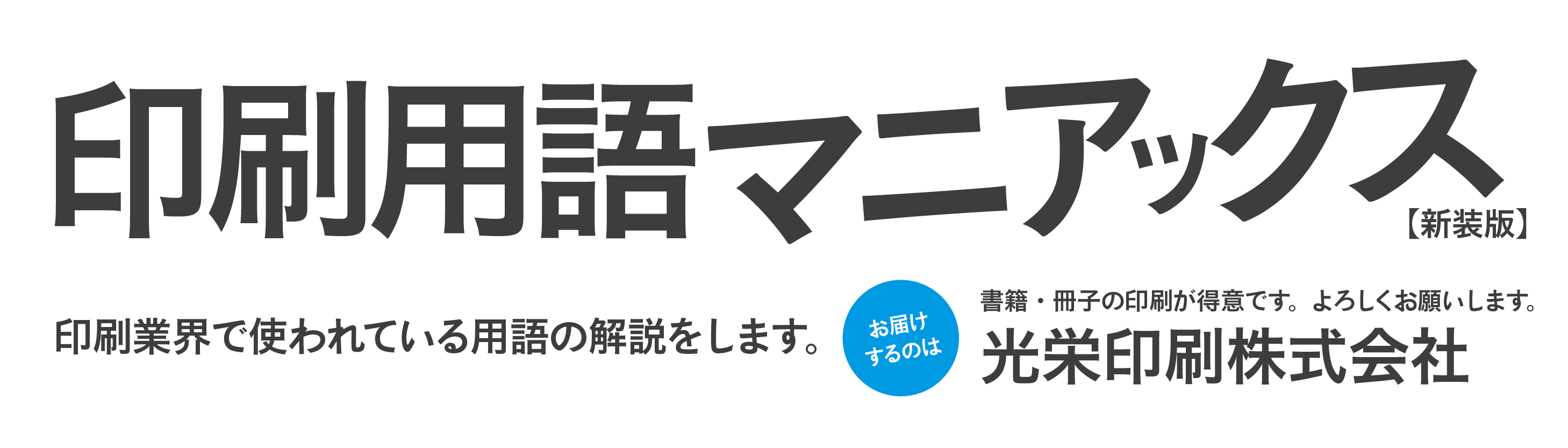網点と網点を重ね合わせると、お互いの網点が干渉して実際の絵柄にはない縞状の模様が生じる場合がある。この現象をモアレとよぶ。 モアレの多くは製版時(スキャニング時)に起こる。例えば、印刷物から写真をスキャニングして流用する場合。印刷物は網点でできているので、網点をスキャニングしてさらに網点にするわけだから、ほとんどの場合でモアレが起こる。また、着物の布地などの細かい繊維を再現しようとする場合もモアレ […]
続きを読むジャンル: 製版
塗り足し【ぬりたし】
紙面の端まで印刷をしたい場合は、「塗り足し」をつけたデータを作成する必要がある。トンボの外トンボ(仕上がりより3mm大きく引かれている)まで塗り足し部分を作っておくことで、内トンボ(仕上がりトンボ)の位置で断裁した際に、端まで印刷された状態に仕上がる。なお、塗り足しを作らず内トンボまでしかないデータで印刷をすると、断裁時に刀がずれて白い部分が出るおそれがある。断裁機は数百枚単位でまとめて断裁を行う […]
続きを読む色校正【いろこうせい】
色校正には主に3つのタイプがあり、それぞれの性質を考慮した上で、どれを採用するかを決定する。 ■本紙校正(平台校正) 校正機という校正刷り専用の機械で、本紙(本番の印刷で使用する用紙)に印刷する。 校正機は、実際の印刷機と構造が異なり、オペレーターが手でローラを動かして1色ずつ印刷している場合が多い(4色いっぺんに印刷する校正機もある)。最初に刷ったインキが乾いてから次のインキを印刷するので、イン […]
続きを読む中綴じの面付け【なかとじのめんづけ】
製本の形態によってページの面付けは違ってくる。無線とじ・あじろ綴じといった、本文を糊で綴じ表紙でくるむものは、丁合時に折丁を順番に重ねていくのに対して、中綴じは中央を針金で綴じる製本なので、折丁を順番に挟むように丁合していく。だから、中綴じの本を無線綴じ・あじろ綴じの面付けで印刷してしまうと、ページ順がめちゃくちゃになる(逆もまたしかり)。 中綴じでは折丁に「ベロ」が必要になる。折丁の片側だけをベ […]
続きを読む